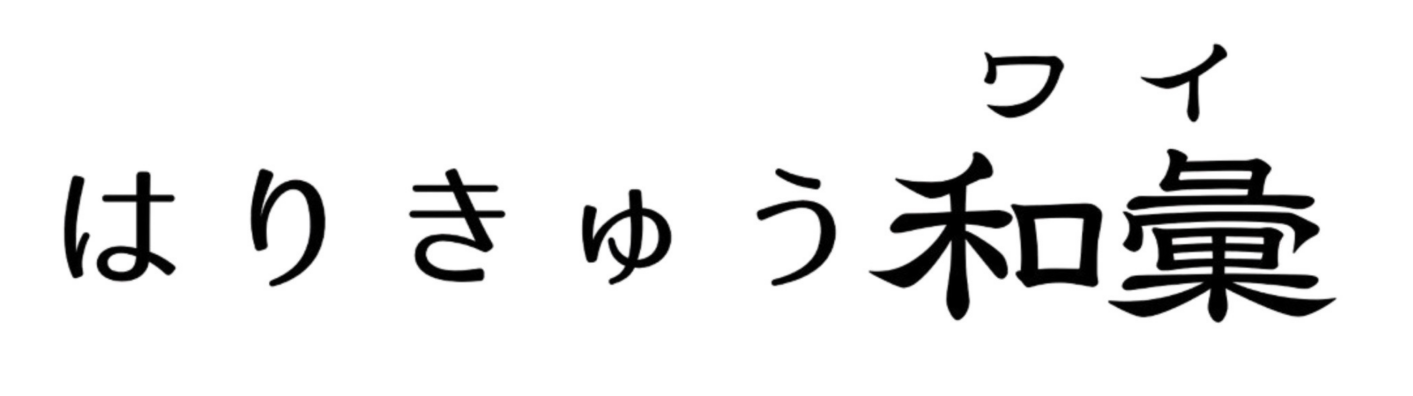霊枢『九鍼十二原篇 第一』③
第六章~第十一章
第六章
刺之而氣不至、無問其數
刺之而氣至、乃去之、勿復鍼
鍼各有所宜、各不同形
各任其所為
刺之要、氣至而有効
効之信、若風之吹雲
明乎若見蒼天
刺之道畢矣
[訳]之を刺して気至らざれば、其の数を問うことなかれ
之を刺して気至らば乃ち之を去る、復た鍼するなかれ、
鍼には各々宜しき所有り、各々形を同じくせず
各々其の為す所に任ず
刺の要は気至って効有り
効の信(しるし)は風の雲を吹くが若し
明らかなること蒼天を見るが若し
刺の道畢(おわ)る
第七章
一、黄帝日、願聞
五藏六府所出之處
[訳]黄帝曰く、願わくは
五藏六府の出づる所の処を聞かん
二、岐伯日
五藏五腧、五五二十五腧
六府六腧 、六六三十六腧
經脈十二、絡脈十五
凡二十七氣以上下
[訳]岐伯曰く
五藏五腧、五五二十五腧
六府六腧、六六三十六腧
経脈十二、絡脈十五
凡そ二十七気、以て上下す
三、所出為井
所溜為滎
所注為腧
所行為經
所入為合
二十七氣所行皆在五腧也
[訳]出づる所を井と為す
溜(りゅう)する所を滎と為す
注する所を輸と為す
行する所を経と為す
入る所を合と為す
二十七気の行く所、皆五輪に在るなり
四、節之交三百六十五會
知其要者、一言而終
不知其要、流散無窮
所言節者、神氣之所遊行出入也
非皮肉筋骨
[訳]節の交、三百六十五会
其の要を知る者は一言にして終る
其の要を知らざれば流散して窮まりなし
言う所の節とは神気の遊行出入する所なり
皮肉筋骨に非ざるなり
第八章
一、覩其色、察其目、知其散復
一其形、聴其動静、知其邪正
[訳]其の色を観、其の目を察し、其の散復を知る
其の形を一にし、其の動静を聴き、其の邪正を知る
二、右主推之、左持面禦之
氣至而去之
[訳]右は之を推すことを主どり、左は持して之を禦す
気至れば之を去る
三、凡將用鍼
必先診脈
視氣之劇易
乃可以治也
[訳]凡そ将に鍼を用いんとするときは
必ず先ず脈を診
気の劇易を視て
乃ち以て治す可きなり
四、五藏之氣已絶于内
而用鍼者
反實其外、是謂重竭
重竭必死、其死也靜
治之者輒
反其氣取腋與膺
[訳]五藏の気、已に内に絶え
而るに鍼を用いる者は
反って其の外を実す、是を重竭と謂う
重竭は必ず死す、其の死するや静かなり
之を治する者は輒ち
其の気に反して腋と膺(上胸)を取る
五、五藏之氣已絶于外而用鍼者
反實其内、是謂逆厥
逆厥則必死、其死也躁
治之者反取四末
[訳]五藏の気、已に外に絶え、而るに鍼を用いる者は
反って其の内を実す、是を逆厥と謂う
逆厥は則ち必ず死す、其の死するや躁(さわが)し
之を治する者は反って四末を取る
第九章
一、五藏有六府
六府有十二原
十二原出於四關
四關主治五藏
五藏有疾、當取十二原
[訳]五藏に六府有り
六府に十二原有り
十二原は四関に出づ
四関は五藏を治することを主どる
五藏に疾有れば当に十二原に取るべし
二、十二原者
五藏之所以禀三百六十五節気味也
五藏有疾也、應出十二原
十二原各有所出
明知其原、覩其應
而知五藏之害矣
[訳]十二原は
五藏が三百六十五節に気味を禀(さず)くる所以なり
五藏に疾有らば応は十二原に出づ
十二原は各々出づる所有り
明らかに其の原を知り、其の応を覩て
而して五藏の(障)害を知るなり
三、陽中之少隂肺也
其原出於大淵、大淵二
陽中之太陽心也
其原出於大陵、大陵二
陰中之少陽肝也
其原出於太衝、太衝二
陰中之至陰脾也
其原出於太白、太白二
陰中之太陰腎也
其原出於太谿、太谿二
膏之原出於鳩尾、鳩尾一
肓之原出於脖映、脖映一
凡此十二原者
主治五藏六府之有疾者也
[訳]陽中の少陰は肺なり
其の原は大淵に出づ、大淵二
陽中の太陽は心なり
其の原は大陵に出づ、大陵二
陰中の少陽は肝なり
其の原は太衝に出づ、太衝二
陰中の至陰は脾なり
其の原は太白に出づ、太白二
陰中の太陰は腎なり、
其の原は太谿に出づ、太谿二
膏の原は鳩尾に出づ、鳩尾一
育の原は脖映(ぼつおう)に出づ、脖映一
凡そ此の十二原は
五藏六府の疾有る者を治することを主どるなり
四、脹取三陽、飧泄取三陰
[訳]脹は三陽に取る、飧泄(そんせつ)は三陰に取る
第十章
今夫五藏之有疾也
譬猶刺也、猶汚也
猶結也、猶閇也
刺雖久猶可抜也
汚雖久猶可雪也
結雖久猶可解也
閇雖久猶可決也
或言久疾之不可取者
非其説也
夫善用鍼者、取其疾也
猶抜刺也
猶雪汚也
猶解結也
猶決閇也
疾雖久猶可畢也
言不可治者未得其術也
[訳]今夫れ五藏の疾有るや
譬えば猶お刺(とげ)の如きなり、猶お汚の如きなり、
猶お結びの如きなり、猶お閇(へい)の如きなり
刺は久しと雖も猶お抜く可きがごとし
汚れは久しと雖も猶お雪(そそ)ぐ可きがごとし
結びは久しと雖も猶お解く可きがことし
閇は久しと雖も猶お決す可きがごとし
或は久疾は取る可からずと言う者は
其の説に非ざるなり
夫れ善く鍼を用いる者の共の疾を取るや
猶お刺を抜くが如くなり
猶お汚れを雪ぐが如くなり
猶お結びを解くが如くなり
猶お閇を決するが如くなり
疾は久しと雖も猶お畢(おわら)す可きが如くなり
治す可からずと言う者は未だ其の術を得ざるなり
第十一章
刺諸熱者如以手探湯
刺寒清者如人不欲行
陰有陽疾者取之下陵三里
正往無殆
氣下乃止
不下復始也
疾高而内者取之陰之陵泉
疾高而外者取之陽之陵泉
[訳]諸々の熱を刺す者は手を以て湯を探るが如くす
寒清を刺す者は人の行くを欲せざるが如くす
陰に陽疾有る者は之を下陵三里に取る
正往して殆きこと無し
気下って乃ち止む
下らざれば復た始むるなり
疾高くして内なる者は之を陰の陵泉に取る
疾高くして外なる者は之を陽の陵泉に取る
参考資料・文献引用
現代語訳「黄帝内経霊枢 上」東洋学術出版
黄帝内経「霊枢訳注 第一巻」家本誠一:医道の日本社